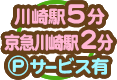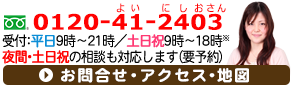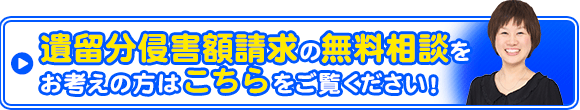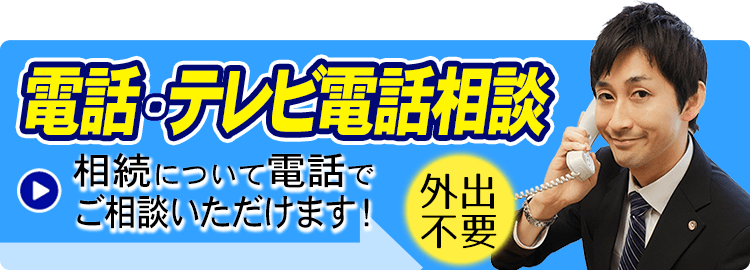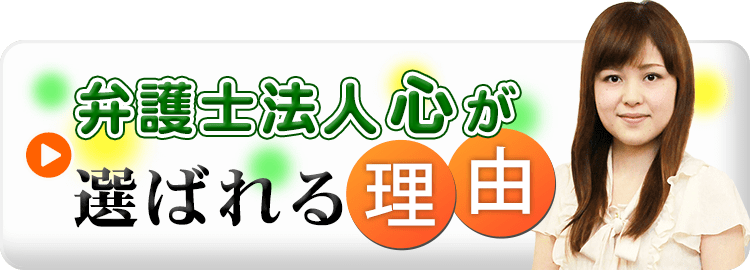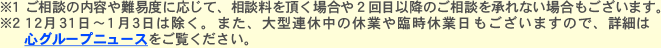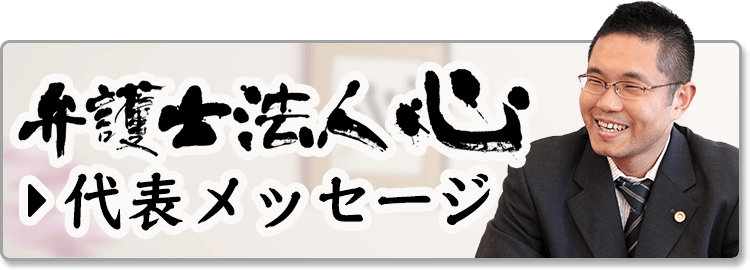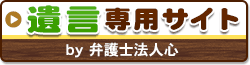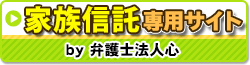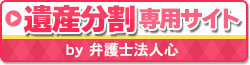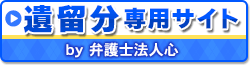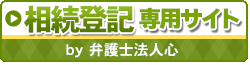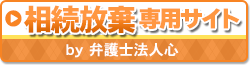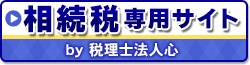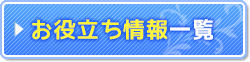遺留分侵害額請求から調停・訴訟への流れ
1 遺留分侵害額請求の概要
一定の相続人に保障されている遺留分の侵害が発生している場合には、侵害している者に対して、遺留分侵害の相当額の金銭の請求をすることができます。
代表的なケースとしては、特定の者に遺産の大半を取得させる旨の遺言が存在していた場合などが挙げられます。
遺留分侵害額の請求をする際には、一般的にはまず遺留分を侵害している受遺者等に対して、内容証明郵便等で侵害額を支払うよう通知をします。
連絡をしても、当事者間では遺留分の支払いについての合意に至れない場合には、裁判所で遺留分侵害額請求調停を行います。
遺留分侵害額請求調停でも合意に至らない場合、最終的には遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
以下、詳しく説明します。
2 受遺者等への通知
遺留分侵害額請求をする際は、配達証明付き内容証明郵便で連絡をすることが一般的です。
内容証明郵便には、遺留分侵害額請求の意思表示と、話し合いをしたい旨を記載します。
遺留分侵害額請求権は、相続が開始したことと遺留分の侵害があることを知ったときから1年で時効により消滅するため、内容証明郵便を用いて、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことを客観的に証明できるようにしておきます。
3 遺留分侵害額請求調停
遺留分を侵害している受遺者等に書面で通知をしても無視されてしまったり、支払額等についての協議がまとまらない場合、裁判所で遺留分侵害額の支払いを求める調停の申し立てをすることになります。
裁判所で調停を行った結果、支払額について合意できた場合には、合意内容に従って支払いを受けることで終了します。